美しきライオンに追われて
神秘体験に慣れていない人たちから見ると、ぼくが「壊れかけてきた」とか「すっかり精神的に参っている」とか、そんな風に見えるのかもしれない。必ずしもそういうわけではない。
話は去年の6月にまで遡る。このブログの初エントリにも少し書いた。
昨夏、仕事上の部下だったアルバイトのちょっとした不手際から、あれよあれよという間にとても手に負えないような巨大なトラブルに巻き込まれて、気が付くと、霊能者の方々にしばしば助言を乞わねばならない窮境に陥っていた。
トラブルの最初の晩、茫然たる気分になって、電気もつけずに暗い部屋のベッドに座り込んでいると、不意に光が閃いた。一目惚れして買ったヤマギワの古いゴールドのデスクライトが、スイッチも入れていないのに、何かを語りかけるように明滅しはじめたのだ。「語りかけるように」というのは、その光の明滅具合が、声の音声信号の波形を光に変換した場合のような微細な震えや抑揚を伴っていたからだ。呆気に取られているうちに、なぜだか、光がどういう回路を通ったのだか、その光の明滅が何を語りかけているのかが、自分に伝わってきたような気がした。
中央へお戻りなさい。
そんな風に聞こえた。光が聞こえるわけない、と誰もが破顔一笑、笑ってしまうにちがいない。けれど、本当の話だ。
小学生の頃、父に初めて買ってもらった工作キットで作った小さなトランジスタ・ラジオを、肌身離さず持ち歩いていた時期があった。帰省のたびに松山から舞鶴へフェリーで向かう船の上で、雑音まみれのそのラジオに耳を傾けていると、時折りその雑音に声や音楽が混入してきたものだ。ああいう感じに近いかもしれない。
やがてその小学生は、30歳過ぎに「自分自身がラジオになってしまった」ことに気付いた。その経緯は、以下の記事に少しだけ書いた。
「中央へお戻りなさい」という天上からのメッセージが、自分が10年以上暮らした「東京へ戻ってこい」という意味なのは何となく分かったが、自分の小説がたとえ多少の評判を得たとしても、純文学のマーケタビリティを考えると東京で暮らしていくのは困難だろうとも感じていた。
アルバイトの不手際とは、「嫌がらせ目的で会社のハサミを何本も隠す」といった種類のもの。まさか、その「消えたハサミ」を皮切りに、こんな16か月の物語が展開されようとは、完全に思いもよらなかった。昨年6月、あの光の明滅の晩には、神様にはこのシナリオが隅々まで見えていたということなのだろう。神様、苦しすぎる、素敵すぎる ordeal = cadeau を贈っていただき、誠にありがとうございました。
世俗的な意味でも、超自然的な意味でも、そのような大音量の「雑音」に晒される前の自分は、毎日少しずつ小説を書いていた。241枚の中編小説を書き上げたあとは、何だか筆力に勢いがついたような気がしたので、20枚限定というルールを自分に課して、短編小説を書いてみた。勤務の傍ら、するすると数日で書けたような記憶がある。
ただ、発表のあてもなく書いたので、いま読み返すと甘すぎるところがあるのを感じる。甘みは主題ではなく、小説内の文脈の参照先との距離の取り方にある。読む人が読めばわかるが、この小説にはスーザン・ソンタグとの距離が近すぎて、やや気恥ずかしい居心地の悪さがあるのだ。
スーザン・ソンタグのことはずっと嫌いだった。一世を風靡した初期の「キャンプについてのノート」の無惨な印象があったので、遠ざけていた感じ。雑誌編集者が「キャンプ」という流行語の波及力がいかに強かったかを語っている回顧録を読んで、ますます嫌いになった。週刊なら週間、月刊なら月間で、何か特別なことが起きていることを商売上「演技」しなければならない出版媒体向けの言説でしかないと感じた。いま読み返しても嫌いだなという感覚は拭えない。不真面目すぎるのだ。
「キャンプ」が何であるかのヒントを58個列挙したリストのうち、42と45は特に酷い。
42――「誠実さ」だけでは充分でないことに気付いたとき、人はキャンプにひかれる。誠実さは、要するに無教養ないし知的偏狭さにすぎないかもしれない。
45――ディタッチメントはエリートの特権である。そして、十九世紀においてダンディが文化の点では貴族の代わりになったように、キャンプは現代のダンディズムである。大衆文化の時代において、いかにしてダンディとなるかという問いに対する答えが、キャンプなのだ。
ところが、バルト読みでありバルト本人とも親交のあったソンタグが、生前のバルトにかけられた最後の言葉は以下のようなものだったという。
やあ、スーザン、いつも真面目だね。
したがって、それがどれほど幼いものであったとしても、問いはさしあたり不可避的にこうなってしまう。不真面目から真面目への転回はどこで生じたのだろう?
後年、自分がソンタグの入門書をあたってみると、別人のように異なる思想家の相貌がそこにはあった。 この新書は新書らしからぬ写真やアート作品が同時に収録されていて、本棚にずっと置いておきたい気分の良さを提供してくれる。
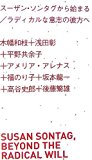
スーザン・ソンタグから始まる/ラディカルな意志の彼方へ (アート新書アルテ)
- 作者: 後藤繁雄,京都造形芸術大学RCES芸術編集研究センター
- 出版社/メーカー: 光村推古書院
- 発売日: 2006/11/01
- メディア: 新書
- 購入: 1人 クリック: 4回
- この商品を含むブログ (12件) を見る
そこから、遠ざけていたスーザン・ソンタグを読み直しはじめて、急速に惹かれていった時期と、先ほどの短編執筆の時期は同じだった。
印象論で語ると、スーザン・ソンタグは「美しく獰猛な雌ライオン」という感じ。日本国籍の世界的知性の持ち主たちも、結構な頻度でガブリとやられている。
そのようなソンタグの意思疎通スタイルを、浅田彰はこう説明している。
それで思い出すのですが、ふつう日本人が話をするときに、こちらが何か言うと相手も適当に頷いてくれるでしょう。スーザン・ソンタグは絶対そうじゃないんです。「あなたが言ったAという点については同意できるけれど、Bという点については異論がある」とこうくるわけですよ。
しかし、こっちも普通の日本人じゃないから(会場笑)、「いや、あなたの言ったB1という点はいいけれどB2という点については異論がある」とこうなるわけです。論争相手というのはおこがましいけれど、ケンカ友だちだと言ったほうがいい。しかし、そのケンカが感情的になることは絶対にないんですね。けっこうきついやりとりをした後でも、スポーツでフェア・プレイと言うけれど、フェアな、つまり公正で美しいやりとりをしたという満足感を与えてくれる、そういう貴重な話し相手でした。
大江健三郎との往復書簡でも、ソンタグが噛みつく場面がある。『隠喩としての病』の著者としては、ファシズムを隠喩として使うことが不適切で容認できないというのだ。ソンタグの厳しい批評眼が細部にまで及んでいるせいで、ちょっとしたことが導火線に火をつけてしまうので、対談はスリリングになりやすい。名インタビュワーをもって鳴る蓮実重彦ですら、冒頭で噛みつかれて、対談を立て直せなかったという噂がある。
ソンタグ: 今日の対話のはじまり方は、私にとって、考えうる最も不幸なはじまり方です。一つには、私が出来るならばまったく関わりたくないと思っているまさにそのことを、蓮實さんの今ご発言は、促進するというか、永続させることに加担するものであるように、私には聞こえるからです。……私の著作に関する書評で、私にまつわりついていたイメージゆえに、あるいは私がすでに有名になり過ぎていたがゆえに批判的な立場を取ったとおっしゃいましたが、そういうものなかったら取らなかったであろう立場を、そういうものゆえに取ったというのであれば、私にとっては考えられないことですし、また、批判すべきことでもあると思うのです。
スーザン・ソンタグと蓮實重彦の微妙な対話 - 高崎俊夫の映画アット・ランダム
読者から見ると、こういう一方的な火花の噴射にも極上の娯楽性を感じてしまうが、当事者は楽ではなかったことだろう。
実は、このような「細部への怒り」は、生来のソンタグ特有のもので、ゴダールの「女と男のいる舗道」は傑作だが、「主演女優は自分の妻」という楽屋落ちネタが最終場面に侵入するのは許せないという意味のことを、初期作『反解釈』に書いている。
ゴダールに触発される側には、(自分も含めて)玉石混交の多数の書き手がいるが、ゴダールを触発する書き手は選ばれた歴史的存在であるのが通例だ。
「戦争にどうコミットするか」が、しばしば非戦闘国の知識人の社会的評価のよすがとなる。管見の限りでは、戦時下のサラエヴォの劇場でベケットの『ゴドーを待ちながら』を上演したソンタグ以上に、ラジカルな政治運動に身を投じた知識人はいない。
世界の耳目を引いたその驚愕のアクションが、ゴダールの『フォーエヴァー・モーツァルト』という傑作映画にどう響いているかは、これ以上ない秀逸な解説を参照してほしい。
この記事の途中で書いた「不真面目から真面目への転回はどこで生じたのだろう?」という幼い問いの答えは、意外に簡単な場所で見つかる。それは転回ではなく、その下にさらに通底する行動規範があったのだ。
「美しき獰猛な雌ライオン」は何を追いかけていたのか? と、もう一度問いを立て直そう。
ある翻訳者が、①美しさと②新しさと③政治性が、ソンタグの追求したものだったと要約しているのを読んで、なるほどと感じた。
①+②=キャンプ、①+③=戦時下での演劇上演。そんな風に考えてみればそう言えないこともなさそうだが、どうもこれらの順列組み合わせでは、ソンタグの中心性を探り当てられていないような気がする。
「美しき獰猛な雌ライオン」にふさわしいのは、状況の変化を知覚する嗅覚の鋭さと、状況の変化に応じて自らの狩猟スタイルを変えられる野性的な柔軟性なのではないだろうか。そして、その狩猟の目的は、人々の中で眠っている価値を、荒々しく揺さぶりたて、目醒めさせることにある。初期には「感覚的」、中期以降はしばしば「挑発的」という一語で評されることの多いソンタグの言動の背後には、そのような「野生の思考」があったように感じられてならない。
例えば、ラジオのような電化製品でさえ、状況論的布置が変わって、それが備え持つ政治性が変容すると、殺人兵器にすらなりうるという歴史的事実に、人々の嗅覚はどれくらい働いているだろうか。
1994年、アフリカのルワンダで、歴史に残るほどの大虐殺が行われた。犠牲者の数はおよそ100万人。国民の10人に一人が犠牲になった。
このときに日本の多くのメディアは、虐殺の要因として宗教や民族紛争などの言葉を使ったが、虐殺する側のフツ族とされた側のツチ族とは、民族・宗教・言語においての差異はまったくない。細かな経緯は割愛するけれど、植民統治下に端を発する政治的な区分なのだ。だから、ツチもフツも互いに縁戚は数多い。住居も混在している。ひとつの家族の中にフツ族とツチ族が入り乱れているケースも、決して珍しくはない。
ならば、何が虐殺へと人々を誘導したのだろうか。テレビがまだ普及していない(しかも識字率も高くない)ルワンダにおいて、ラジオは唯一の国民的な娯楽だった。フツ族向けのラジオ放送局が、ツチ族の危険性をしきりに煽り、その結果、「彼らを殺さないことには自分たちが殺される」との意識が植え付けられ、最終的にあの未曾有の虐殺は始まった。
1998年に放送されたNHKのドキュメンタリー『なぜ隣人を殺したか~ルワンダ虐殺と扇動ラジオ』では、フツ族向けのラジオ番組のDJが、「なぜ虐殺を扇動するような放送をしたのか?」との質問に対し、「殺せなどとは一言も言っていない。俺はただ、危ないぞと言っただけだ。」と弁明している。
虐殺前のラジオ放送の内容を聞けば、確かに彼はツチ族を「汚くて病原菌を撒き散らすゴキブリ」などと形容しながら、「放置すれば危険だ」的なことは言っているが、直接的に殺せとは言っていない。それはまるで、かつてナチスがユダヤ人をシラミに喩えながら、駆除の必要性を国民に訴えたことを想起させる。(シラミはチフスを媒介する。)
これがプロパガンダだ。メディアは危機管理意識を刺激する。そして人は、この刺激に最も弱い。なぜなら群れで生きるからだ。
死のわずか数年前、9.11同時多発テロという「グラディオ作戦」を目撃したソンタグは、一斉に感情的に集団動員されていく自国民たちの前で、それに逆らう孤立無援の論陣を張って、集中砲火を浴びた。
初期通り、9.11同時多発テロを成功させた陣営は、そのわずか一か月半後に「自由の国アメリカ」を終わらせてしまう米国愛国者法を成立させた。同時多発テロも含めて「計画通り」なのだから、その手回しの速さに驚くべきではない。
同時多発テロ直後にソンタグが孤立しつつ立ったのとほぼ同じ場所に、ようやく良識あるアメリカ国民が集まって、いくらかでも自由を取り戻したのは、同時多発テロから4年も経過したあと、ソンタグの死後のことだった。
書物は死者たちの言葉に耳を傾けることのできる特権的なメディアだ。
ソンタグの翻訳著作はほぼ出揃いつつある。
著作を読めば、美しさと新しさと政治性を追い求めた「美しき獰猛な雌ライオン」の唸り声が聞こえるような気がする。その唸り声を背後に聞けることの幸福を噛みしめる暇もなく、自称 Stray Rabbit は、彼女の嗅覚ならこの状況で次にどう走るのかを想像しながら、彼女よりはるかに短いストライドで、逃げるように小走りしていくしかないと考えているところだ。
(「壊れかけのradio」のヴォーカリストによるカバー)

